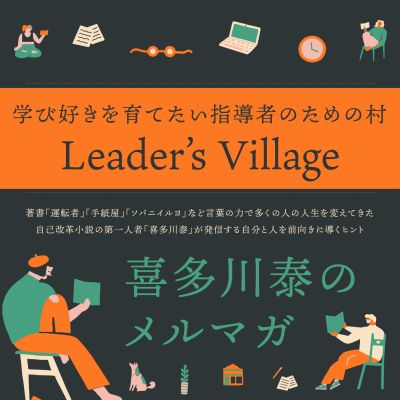Vol.115 「大差は微差でしか生まれないんだ」
喜多川泰のメルマガ「Leader’s Village」喜多川泰のLeader's Village Vol.115号です。
その人に何ができるか、どんなことができるようになるか。
それらを決めるのは、持って生まれた才能や能力が大きな要素だと思われがちだけど、実はそれらはそれほど大きな要素ではないと僕は思っている。
これまでたくさんの高校生を指導してきたが、個々の持って生まれた能力差というのは実はほとんど感じない。もちろん、飛び抜けた記憶力や直感力、処理能力を持った子がいるのも事実だが、全体の1%もいない。
そういう子にとって受験はハードルでもなんでもない。飛び抜けた存在なんだからどこを受験しようがその子は合格する。
別の言い方をすると、どの大学を受験しようとも、合格ラインを競い合っている同レベルの生徒たちの中にそういう人はいない。定員が100人だとしたら、そういう特殊能力を持った人が一人いるかいないか。超難関大学でも、多くて10人というところだろう。残りの定員は自分と能力的には大差ない人たちが席を競っていることになる。
ところが、能力的には大差がないのに、結果や点数、偏差値的には「大差」がついているんですね。
理由はそれまでの日々の過ごし方の中にある、ほんのちょっとした「微差」が積み重なるから。
「帰ってすぐやる」か「あとからやる」の違いだったり、
「とりあえず言われたところまではやろう」か「もう一回間違えたところもやっておこう」かの違い。
はたまた、
「今日、単語覚えようと思ってたけどやれなかったから明日にしよう」か「隙間の時間を使って覚えようと思っていたところは、今日も完璧にできるようになった」かの違い。
そういう微差が積み重なって大差になる。
答えを見ても、解説を聞いても、それは自分には解ける気がしないと感じるような難しい数学の問題をスラスラ解くクラスメイトを見ると、数学的センスが羨ましく感じるかもしれないが、実はそのクラスメイトにとっても最初は同じだった可能性が高い。単純に同じ問題をこれまでに見たことがあって、その解き方を覚えていたに過ぎないことがよくあるが、解けない人はそれに気づけずに、
「あの子は賢い」
または
「自分は数学が苦手」
という言葉で片付けてしまう。
どちらの言葉もやめた方がいい。「だからしょうがない」と自分にはできなくてもいいことを正当化することになりかねないから。
そして、経験はさまざまな知識の繋がりを生み、学びや理解を加速させていく。英単語を一つも知らない人が100個覚えるのと、2000個覚えている人が2100個に増やすのは、同じ100でも、かかる時間も必要な労力もまったく違うが、それは能力差ではない。0から100の人には起こり得ない、知識の繋がりによる加速が2000から2100の人にはたくさん起こる。
別の人で起こるのではない。同じ人のなかで起こるのだから、能力差ではないことがわかるだろう。
だから僕は高校生たちに常にこう伝えていた。
「大差は微差の積み重ねでしか生み出すことはできない」
と。
この続きを見るには
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)
これはバックナンバーです
- 喜多川泰のメルマガ「Leader’s Village」
- 「どんな話をすれば、聞く人のやる気を引き出せるのか」先生や管理職など、人前で話をすることが多いリーダーは、常にそのことを考え、悩み、ネタ探しをしていることでしょう。頻繁に人前に立つのに話題が尽きない人は、学び好きであることと、独自の価値観を持って世界を見ているという点で共通しています。このメルマガでは、独自の価値観を創造していこうとする学び好きの人が、価値観の変容を起こし、明日、部下や生徒の前で話したくなるような内容を発信していきます。いただいた質問とのやりとりを通じて、一つの「村」のように情報交換ができる場にしていこうと思っています。「Leader’s Village」開村!村民募集中です。