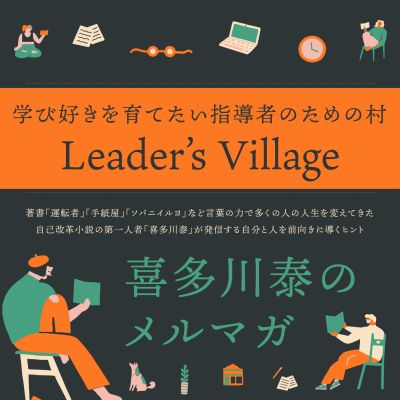Vol.98 「子どもを孤独から救え!」
喜多川泰のメルマガ「Leader’s Village」喜多川泰のLeader's Village Vol.98号です。
かつて、メルマガ Vol.20で「友達」について書いたのを覚えてる?
「友達は多い方がいい」
一般的にそう言われることが多いけど、世の中の人はあまりにもその考え方にとらわれすぎているかもしれないんですね。
だから、自分にとって「友達とは?」という定義をしてみては?という提案をさせてもらった。(以前読んだという人も、まだ読んでいないという人も Vol.20も合わせて読んでね)
今の時期、中学3年生の多くは受験勉強で忙しく、それどころじゃないかもしれないと思いきや、受験と同じくらい、いや、実はそれ以上に気になっていることがあるんですね。
それは、
「高校行ったら友達できるかな?」
ということ。
意外ですか?
でも、彼らにとっては結構切実な問題だったりする。
というのも、それまでの友達はというと、作り方も何も気づけばいたわけです。
幼稚園や保育園に通う年齢で「どうやったら友だちになれる?」なんて誰も考えない。
自分以外の他者のことを、
「おともだち」
と呼ぶ世界でしょ。つまり、関係性は問わず自分以外はみんな友だちなんですね。
話が合うとか、性格が合うとか、一緒にいて楽しいとか、そういう条件は一切ない世界。
小学校に上がったときもほぼ同じ感覚。
「みんなともだち」
中学生になるときはすでに、話が合うとか、性格が合うとか、趣味が似ているとかで、友達とそれ以外は区別されていただろうけど、公立の小学校から中学校に進学するほとんどの子は、その人間関係を持ったまま中学に入学する。中学に行っても小学校からの友達がいるわけです。
だから、中学から高校という変化が彼らが経験するほぼ初めての、知っている人が誰もいない人が集まる世界になる可能性が高いんですね。
そこで改めて考えて、わからなくなる。
「あれ、友達ってどうやって作るんだっけ?」
一方で、大学や社会に出るとき、転職する際など、その後の人生では何度も、知っている人が誰もいない世界に入っていく機会が訪れるけど、ほとんどの人が、
「友達できるかな?」
ということはあまり心配しないですよね。
必要なのは「一緒にいてくれる友達」ではなく、「価値観を共有できる仲間」であることがなんとなくわかっているからだっていうのは Vol. 20 でも伝えた通り。
ということは
「友達できるかなぁ」を心配しなくなる分岐点は、やはり、中学そして高校時代に訪れることになる。
この続きを見るには
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)
これはバックナンバーです
- 喜多川泰のメルマガ「Leader’s Village」
- 「どんな話をすれば、聞く人のやる気を引き出せるのか」先生や管理職など、人前で話をすることが多いリーダーは、常にそのことを考え、悩み、ネタ探しをしていることでしょう。頻繁に人前に立つのに話題が尽きない人は、学び好きであることと、独自の価値観を持って世界を見ているという点で共通しています。このメルマガでは、独自の価値観を創造していこうとする学び好きの人が、価値観の変容を起こし、明日、部下や生徒の前で話したくなるような内容を発信していきます。いただいた質問とのやりとりを通じて、一つの「村」のように情報交換ができる場にしていこうと思っています。「Leader’s Village」開村!村民募集中です。